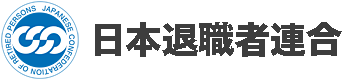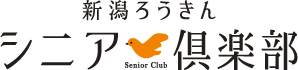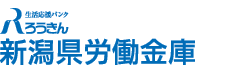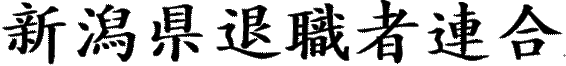新潟県退職者連合 会長
山田 太郎

今年は戦後80年、被爆80年を迎え、全国各地で平和の集いや式典などのセレモニーが開催されてきました。80年という節目の年であるだけに、長い戦後史の総括があらゆるところで求められていますが、そう簡単に結論が出るものではないと思います。
例えば、あの戦争が侵略戦争か自衛のための戦争か、有識者の中でも見解は分かれるところではないかと思います。この80年の間に、私の祖父や父を含め、戦争体験世代が減少しています。戦後の日本社会の中で戦争体験者の存在は、ある意味で日本が再び軍事大国化することへの抑止力として、それなりの機能を果たしてきたのではないかと思います。
併せて、職場や地域においては、平和団体や護憲勢力の活動、労働運動との連携など、反戦・平和の根強い運動がありました。しかし、その活動や意識も高齢化や時の流れとともに風化してきたように感じます。戦争体験者の減少も含め、こうした重しがとれようとしている中で、日本の防衛政策の根本的な転換が行われてきました。
振り返れば、安倍政権以来の一連の安保関連法や安保三文書の強硬採決により、防衛費の増額(5年間で43兆円)が始まっています。また、専守防衛をかなぐり捨て、敵基地攻撃能力が肯定され、沖縄をはじめ南西諸島に自衛隊のミサイル基地が次々と配備されており、まさに新たな戦争前夜の様相を呈しているのではないかと思います。
また、世界に目を向ければ、長引くロシアのウクライナ侵攻やイスラエルのパレスチナ・ガザ地区攻撃は、兵士のみでなく高齢者、女性、子供たちなど多くの命を奪っています。核兵器を使用した広島・長崎の惨劇がどのようなものか想像すらできないP大統領は、核兵器の使用も示唆しており、同じ時間軸で、この瞬間を生きる人間として、とても受け入れ難い現実です。
連合は、戦後80年を契機に核兵器廃絶と世界の恒久平和を希求し、1,000万署名の取り組みを春から進めています。退職者連合も、この活動に積極的に協力しています。世界各地の戦争(紛争)に一日も早い停戦を求め、「戦争はノー」の声を上げていかなければなりません。
これまで私たちは平和憲法の庇護の下、有事とは縁のない時間を過ごしてきましたが、戦争体験者のいなくなっていくこれからの社会の中で、戦後80年の意味や意義を社会に対しても、自分自身に対しても、また、次世代のためにも問い続けていく必要がありますし、退職者連合の大きな運動課題としていきたいと思います。