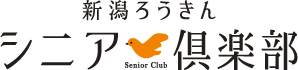三十一文字に魅せられて
長浜 武士(村上地域退職者連合)
私は趣味の一つとして現在も新潟日報読者文芸欄の「歌壇」に投稿を続けていますが、その思い出について少々綴って見ました。
私が三十一文字(みそひともじ)、いわゆる短歌に魅せられたのは高校三年の時に「石川啄木」の歌集を行き付けの本屋で何気無く手にした時からです。中卒で稼ぎに出るのが当たり前の様な家庭なのに、友達と試しに受験した高校に合格し親に叱られながら何とか入学をさせてもらった自分には、簡単に本を買えるような金は有りませんでした。粗末なざら紙の文庫本、石川啄木の「一握の砂」を自分の物にしたのは、夏休みに地曳き網引きのアルバイトで得た金で買った時でした。
大袈裟な様ですが、以来この啄木の歌集を私は常に手放さず暇さえあればその一首一首を読みながら感動していました。国語の授業で「和歌」は知っていましたが、それは私達には全く無縁のものと思っていただけに衝撃的でした。誰にでも分かる平易な言葉、そしてなによりも貧に苦しむ歌に自分を重ねて感傷に耽りながらも、自分でも短歌が作れるのではないか、作ってみたいと言う思いから時々地元紙「新潟日報歌壇」に投稿を始めました。
やがて郵便局に就職し、私の短歌が初めて新聞の活字になったのは、次の歌でした。
「配達を了えし村村をこの道に見渡せばはや靄かかり居り」
吉野秀雄(昭42年没)選。
新潟日報の歌壇は現在も脈々と続いておりますが、当時、私の歌を多く採っていただいた、宮柊二(昭61年没、現在宮柊二記念館あり)選の拙詠をご紹介し、雑文を閉じます。
「月賦にて妻に買いたる指輪持ち帰る夜道に雨はそぼ降る」
「木工に従ふ妻よわが椀を受ける手指の節あらわなり」